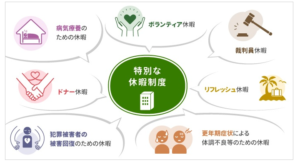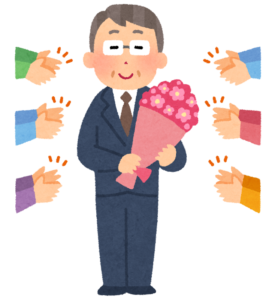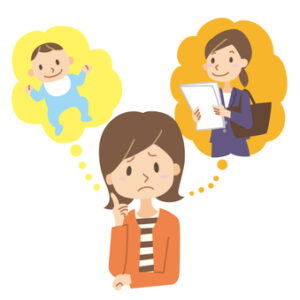こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
パートタイマー、アルバイト、契約社員等、いわゆる非正規で働く人の割合が全労働者の35%を超える状況が続いています。非正規で働く人材を活用している企業では、同一労働同一賃金をはじめとしたパートタイム・有期雇用労働法の遵守が大きな課題となっています。以下では、パートタイム・有期雇用労働法で規定されている正社員転換推進措置について確認します。
[1]非正規雇用労働者の定義
非正規雇用労働者とは、正社員(通常の労働者)と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者と、期間の定めがある労働契約(有期契約)で働く労働者のことを指します。これらの労働者は、パートタイム・有期雇用労働法が適用され、正社員とは異なる対応が求められています。
[2]正社員転換推進措置
労働者と企業が結ぶ雇用契約の内容は、原則として、労働者と企業に委ねられています。ただし、企業は、非正規労働者を雇用する場合には、正社員への転換を推進する措置を講じることが求められており、その内容は、次のいずれかとされています。
- 正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っている非正規雇用労働者に周知する。
- 正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っている非正規雇用労働者にも応募する機会を与える。
- 非正規雇用労働者が正社員へ転換するための試験制度を設ける。
- その他正社員への転換を推進するための措置を講ずる

[3]制度運用時の留意点
正社員への転換には、転換の要件として、勤続年数などの一定の要件を課すこともできるとされています。この要件については、企業の実態に応じたものであれば問題ないものの、必要以上に厳しい要件を課している場合には、正社員への転換を推進する措置を講じたとは判断されないこともあります。なお、企業に求められていることは正社員への転換を推進する措置を講じることであって、正社員に転換することまでを求めるものではありません。
若年層の人口が減少する中、正社員を中心とした事業活動の運営では、十分に人材確保ができず、働く日数や時間に制限のある非正規雇用労働者を活用する場面が多くなっている企業もあるかと思います。その際には法令で求められている対応が適切にできるように進める必要があります。
■参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者(有期・パート)の雇用」
福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)