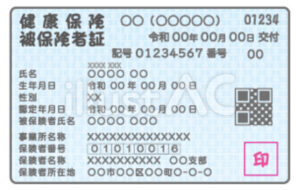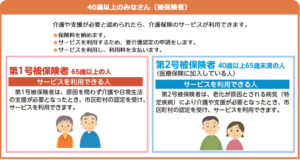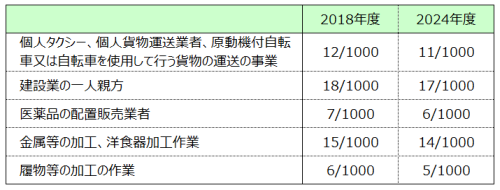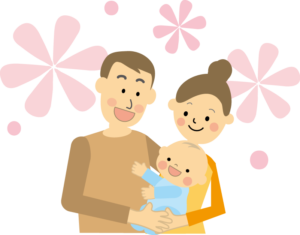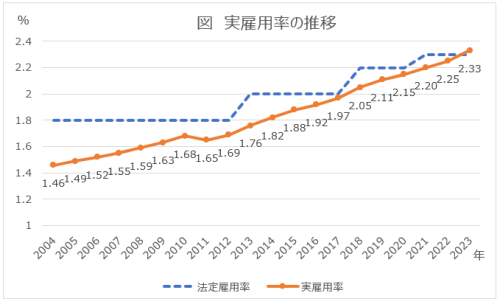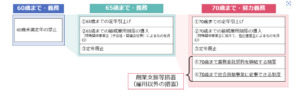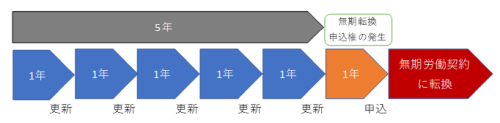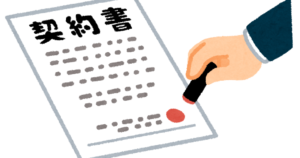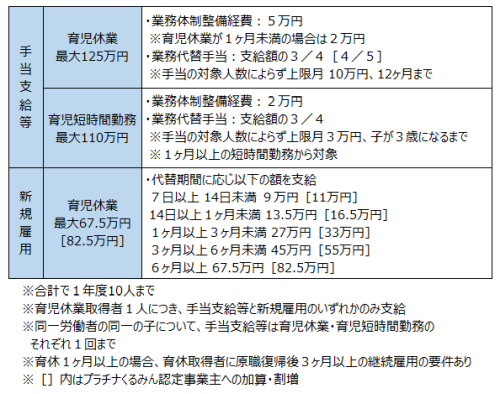こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
近年の労働基準行政においては過重労働対策に重きが置かれており、労働者に対する安全や健康に対する配慮義務が強く求められています。加えて、事業場の労働者数が常時50人以上になると、労働安全衛生法の中で実施が求められる事項があります。以下ではその内容をとり上げます。
[1]常時50人以上の労働者を使用する事業場とは
まず常時雇用する労働者の定義を確認します。労働安全衛生法の対象となる「労働者」とは、原則、労働基準法と同じとされています。次に「常時使用する」とは、企業の通常の状況により判断するとされており、臨時的に雇い入れた場合や欠員を生じた場合は労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要はないものの、パートタイマー・アルバイトであっても臨時的な雇入れでなければ、常時使用する労働者数に含める必要があるとされています。
そして、労働安全衛生法では、職場で働くすべての労働者の安全を守る法律であることから、派遣労働者を受け入れている事業場は、常時雇用する労働者数に派遣労働者を含めて算出することになります。例えば、事業場で雇用している労働者数が45人で、派遣労働者が5人いる場合には、合計50人となります。
[2]労働者50人以上の事業場で実施が求められている事項
労働者数が50人以上の事業場において実施が求められている事項は、以下の5点です。
この中で、衛生管理者の選任については、業種を問わず選任する必要があり、50人以上の事業場が複数ある場合は事業場ごとに選任することになります。選任後、衛生管理者が休業等やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理の選任が必要です。その際、代理者の資格については、通達(昭和23年1月16日 基発第83号、昭和33年2月13日 基発第90号)で、以下のように示されています。
- 衛生管理者の資格を有する者がいれば、その者に代理させること
- 上記によることが不可能または不適当な場合は、保健衛生の業務に従事している者または保健衛生の業務に従事した経験のある者
また、同じ通達の中で、衛生管理者が長期にわたって職務を行うことができない場合には、別に衛生管理者を選任することとされています。そのため、衛生管理者が育児休業や介護休業などの取得で長期休業に入る場合については、別に選任する必要があります。
年度末や新年度を迎える中で、従業員の入退社が多い時期になります。労働者数を確認し、50人以上の事業場に該当する場合は、上記の事項を着実に実施していきましょう。
■参考リンク
東京労働局「衛生管理の充実」
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
厚生労働省「健康診断結果報告の提出の仕方を教えて下さい。」
福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の制定及び変更、制度設計、労務相談、各種助成金に関するご相談、申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)